明鏡止水(めいきょうしすい)の漢字をジーッと見つめて…意味わかりますか?
止水って断水のこと?明鏡はステキな意味がありそうですが、止水はどう考えてもマイナスイメージです。
「良いこともあれば悪い事もある」というところかな?さてさて、意味は何かしら?と思いましたら、なんと同じような意味でした。
止まってる水ってそんなふうに捉えるんだ、今の日本で止まってる水って言ったらアメンボが泳いでる池ですかね。きっと「止水」が生まれた頃は、キレイな湖や池があったのでしょう。
明鏡止水は、人間の偏見なんかをフッ飛ばして行きつく菩薩のような境地のことです。なかなか難しいけれど、澄んだ心を取り戻したい方にこそ、座右の銘にして欲しい四字熟語です。
この記事では、明鏡止水(めいきょうしすい)の意味、座右の銘としてお勧めな方、由来、類義語をご紹介します。
明鏡止水(めいきょうしすい)の意味を知るだけでも落ち着くよ
明鏡止水の意味を調べてみました。
めいきょう-しすい【明鏡止水】
意味曇りのない鏡と、静かな水面。心が明らかに澄んでいて、静かに落ち着いていることのたとえ。
引用元:大修館 四字熟語辞典
「曇りのない鏡と静かな水面」をイメージすると、こんな光景が浮かんできました。

このように、鏡のごとくキラキラと輝く湖のような心情のことを明鏡止水と言います。
明鏡止水は自己嫌悪を感じやすい方の座右の銘としてお勧め!
煩悩だらけの私たち、明鏡止水の境地になれたらどんなに楽になるでしょう。
「煩悩があっての人生でしょ」と開き直れる方は別として、「こんな気持ちになる自分が嫌なんです」と自己嫌悪を感じやすい方へ、明鏡止水を座右の銘にすることをお勧めします。
- 相手の誉め言葉を素直に受け取れない、もしかして裏があるのかも?と深読みする方
- 自分の方がキレイなのに彼女の方がチヤホヤされてない?とやっかんでしまう方
- 切り分けたケーキを見て自分の方が少ない…自分の存在が軽視されているのでは?といじける方
- 仕事のできる部下に気持ち良く缶コーヒーをおごれない方
- バーゲンセールで他の誰よりもお得な商品をゲットしようと戦闘態勢に入る方

「あなた明鏡止水って四字熟語、知ってる!?」
「あなたこそ知らないでしょ!」
明鏡止水を座右の銘にした皆さんが、心が澄みわたり落ち着いた心情になれますように。
明鏡止水の由来をふたつの書物から紹介するよ
明鏡止水の由来を調べたところ、中国の書物に由来と思われる一説がありました。
「荘子」から
「明鏡」と「止水」、それぞれ「荘子」の中に面白い話があります。
原文はないですがわかりやすく訳された書籍をご紹介します。
まずは「明鏡」から。
「明鏡」の話の主人公は、孔子が活躍した時代より少し前にいた申徒嘉(しんとか)という前科者です。刑罰によって、片足を切り落とされてしまったという過去があります。
その申徒嘉がある師のもとで勉学に励んでいたとき、同門のエリートから、自分にもっと敬意を払えと言われます。これに対して申徒嘉は、「同じ師のもとで学ぶ以上、あなたとわたしは対等だ」と主張。さらに、「賢人と付き合えば、磨かれた心に曇りがなくなるものだというのに、あなたは立派な師のもとで学んでいながら、まだ偏見という曇りが消えないのか」と、相手をやりこめたのでした。
引用元:すっきりわかる!超訳「故事成語」事典PHP文庫 造事務所
「偏見という曇りが消えないのか」と偉そうなエリートをやりこめた申徒嘉の言葉にスッキリしますね。つぎは「止水」のお話です。
一方、「止水」の話には、王駘という人物が登場します。孔子と同時代の人で、孔子と同じくらい多くの門弟がいましたが、王駘もまた、申徒嘉と同じく過去に罪を犯し、片足を切り落とされる罰を受けていました。
そんな人物が、孔子と同等の名声を得ていることに、孔子の弟子は不満に思い、孔子にたずねます。「前科者が、なぜあんなに慕われているのでしょう?」
すると王駘を高く評価していた孔子がこう言いました。「自分が前科者であり障害をもつことを、彼はもう気にかけていないのだろう。それは、静止した水のように穏やかな心境に達しているからだ。そういう人物はおのずと人を集めるものだよ。自分も機会があれば、王駘に教えを受けたいくらいだ」と。
引用元:すっきりわかる!超訳「故事成語」事典PHP文庫 造事務所
このふたつの熟語は、同じ「荘子」の話であることと、人徳のある前科者をやっかむ者を諭すというエピソードが共通していることから、意味を同じくするものとして四字熟語となり、使われるようになったのではないでしょうか?
…と、荘子で四字熟語になったかと思いきや、後の時代に書かれた淮南子にも「明鏡止水」は別々に登場します。
「淮南子(えなんし)」から
武帝(前漢の第七代皇帝)の頃、淮南王の劉安(皇族・学者)が学者を集めて編纂させたと言われる思想書「淮南子(えなんし)」からの引用です。
出典人の流沫(りゅうまつ)に鑑(かんが)みる莫(な)くして止水に鑑みるは、其(そ)の静かなるを以(もっ)てなり。形を生鉄(せいてつ)に窺(うかが)ふ莫くして明鏡に窺がふは、其の易(たひ)らかなるを以てなり。
〈淮南子、俶真訓〉
引用元:大修館 四字熟語辞典
「人が自分の姿を見ようとする時は、流れている水ではなく、静かな水(止水)に姿を映してみるだろう。また鉄ではなく、曇りのない平らな鏡(明鏡)に映してみようとするだろう」ということです。
これは「自分の姿を見るなら、止まっている水の方が鏡みたいによく見えるよ!」ではなく、「心静かに曇りのない心でものごとをみることが大事ですよ」という意味です。
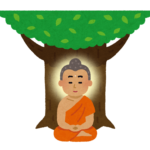
荘子と淮南子か~悩むな~あ、彼女の名前じゃないよ
まとめ荘子や淮南子の「明鏡」と「止水」は、どちらの書物でも意味や使い方は同じです。淮南子は荘子より後に書かれているため、淮南子が編纂された漢の時代以降に「明鏡止水」となり、四字熟語として使われるようになったのではないでしょうか?
明鏡止水の類義語はゲーム好きなら知ってるかも?
明鏡止水の類義語を調べると、ゲームに出てくるようなカッコいい四字熟語ばかりでした。
- 「心頭滅却(しんとうめっきゃく)」悟りの境地にいたること。
- 「則天去私(そくてんきょし)」自然の道理に従って私心を捨て去ること。
- 「無想無念(むそうむねん)」「無念無想(むねんむそう)」無我の境地に入り何も思わないこと。

行くわよ!心頭滅却の術!
まとめ
明鏡止水(めいきょうしすい)の意味は、「心が明らかに澄んでいて、静かに落ち着いている」です。
なかなか到達することが難しい心の境地ではありますが、己の小ささに気が付き、愕然とした覚えのある方、こんなんじゃいけない、大きな器になりたいと願う方にこそ、明鏡止水を座右の銘とされることをお勧めします。
その由来は中国の荘子や淮南子の一説にあり、どちらも同じ意味として使われています。あとに編纂された淮南子の時代以降に四字熟語として使われるようになったのでは?と推測します。
明鏡止水の類義語として、心頭滅却、則天去私、無想無念、無念無想などがあります。
この記事では、明鏡止水の意味、座右の銘としてお勧めな方、由来、類義語をご紹介しました。





